従業員の逮捕
![]() 2025年 10月14日
2025年 10月14日

従業員が休日に痴漢行為で逮捕された場合、会社は懲戒解雇することは可能なのでしょうか。今回は、痴漢行為に関する懲戒解雇の可否について、私生活上の非行行為の懲戒処分の原則をはじめ、分かりやすく解説します。
私生活上の非行行為で懲戒処分は可能か
私生活上の非行行為とは?
①業務とは無関連、②就業時間外、③企業施設外に行われた非行行為のこと
原則:私生活上の非行行為では懲戒処分はできない
例外:会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような行為の場合
①性質や内容・情状
②会社の事業の種類・態様・規模
③会社の経済界に占める地位、経営方針
④その従業員の会社における地位・職種
上記等の事情から総合的に判断し、客観的に悪影響が認められるもの
私生活上の痴漢行為による懲戒処分
今回は懲戒処分の中でも、諭旨解雇と懲戒解雇について考えていきます。
痴漢行為の場合には裁判所で判例が分かれることが多く、個別的事情を考慮し判断されています。
①痴漢行為の態様・刑罰の内容
諭旨・懲戒解雇が有効になりやすい要素
- 不同意わいせつ(旧強制わいせつ)にまで至っている(例えば、下着の中に手を入れる(入れさせる)、衣服の上からでもしつこく触り続ける、押し倒すなどの行為を伴うなど)
- 迷惑防止条例違反で、懲役刑に処せられている(同種前科があるなど)
諭旨・懲戒解雇が無効になりやすい要素
- 迷惑防止条例違反で、少額の罰金刑に留まっている
②前科・前歴の有無、日常の勤務態度
諭旨・懲戒解雇が有効になりやすい要素
- 痴漢行為等で前科や前歴がある
- 同種の痴漢行為で懲戒処分を受けたことがある
諭旨・懲戒処分が無効になりやすい要素
- 前科・前歴や懲戒処分歴がない
- 日ごろの勤務態度が良好である
③その他
諭旨・懲戒解雇が有効になりやすい要素
- 管理職など要職についている
- 就業規則の複数の懲戒規定・服務規程違反である
労務提供できないことを理由とした解雇
上記の通り、痴漢行為で逮捕されたことを理由に懲戒解雇することは難しいと言えます。
しかしながら、逮捕を理由に長期間欠勤となる可能性もあります。そのような場合には、痴漢行為の疑いがあることや逮捕されたこと自体ではなく、それにより「長期間労務提供が行われないこと」を理由とした普通解雇も検討すべきでしょう。
こんな時どうする?
Q1 起訴・不起訴が未確定なまま、従業員が釈放されました。どのように対応すればよいですか?
起訴・不起訴が未確定とはいえ、雇用契約は継続しているため、原則は出勤させることになります。混乱を避けるため、自宅待機を命じることも可能です。但し、調査段階では従業員に責任があると決まったわけではないため、賃金については全額支払うことが妥当でしょう。
Q2 従業員の家族から「逮捕中に出勤ができないため、年次有給休暇を申請したい」と申し込みがありました。受理すべきですか?
年次有給休暇の利用目的については法的に制限を設けることができないため、申請があった場合は原則として認める必要があります。あわせて、休暇取得に際しては必ず本人の意思を確認するとともに、取得手続や運用ルールを明確に定め、従業員に周知しておくことが重要です。
Q3 私生活上の痴漢行為で懲戒処分となった例を教えてください。
小田急電鉄事件では、電車内で女子高校生の臀部をスカートの上から撫でまわしたうえ、右手をそのスカート内に差し入れ、右手指でその左臀部を撫でまわすなどした、従業員の懲戒解雇が有効となっています。
判断要素として、下記が挙げられました。
①決して軽微な犯罪ではない
②職務に伴う倫理規範として痴漢行為を行ってはならない立場
③半年前に同種の痴漢行為で罰金刑に課せられ、昇給停止・降格処分を受け、始末書を提出していたこと
一方、東京メトロ事件では、通勤のため乗車していた電車内で、当時14歳の女性の右臀部付近および左大腿部付近を、着衣の上から左手で触るなどした、従業員の諭旨解雇は無効となっています。
判断要素として、下記が挙げられました。
①悪質性が高いとまでは言えない
②罰金20万円の略式命令にとどまっている
③前科・前歴や懲戒処分が一切なく、勤務態度にも問題がなかった
④起訴・不起訴以外の要素を十分に検討した形跡がうかがわれたこと、起訴の経緯など
従業員の私生活上の行動を取り締まることや
私生活上で行った行為に対して懲戒処分を行うことは非常に難しいと言えます。
日ごろから行動指針の共有など社員教育を行い、会社の看板を背負っていることを自覚してもらうことも大切です。
また、服務規程や懲戒規定の整備や定期的な見直しを行い、予期せぬ事態にも対応ができる体制をととのえましょう。
アイプラスでは、各企業様の実情に即した就業規則の策定や改訂、各種社員研修も行っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
社労士の労働相談
従業員の採用から、入社・配置・育成・退職まで、1人ひとりの労務管理と
会社全体の就業環境や評価体制の整備まで。
労働関係法令を根拠に、判断軸やトラブル時の対応方法をアドバイスします。
![]()
採 用
□ 採用選考時の留意点
□ 採用内定者フォロー
□ 労働条件の決定方法
□ 労働条件の明示内容
□ 雇用契約の締結
![]()
配置・育成
□ 勤怠管理の方法
□ 管理職の指導問題
□ 配転など人事発令
□ 昇給・昇格・降格
□ 懲戒処分の方法と流れ
![]()
退 職
□ 従業員からの退職希望
□ 会社からの退職の要請
□ 競業避止義務の有効性
□ トラブルにならない解雇
![]()
企業内規定の整備
□ 就業規則・諸規定の整備
□ 規則等の法規制対応診断
![]()
組織再編の支援
□ IPO準備のための労務監査
□ 人事制度・労働条件の統一
□ 労働条件不利益変更の解決
![]()
労務監査
□ 労働関係法令違反の調査
□ 労務状況改善・定期監査
従業員の採用から退職まで、日々の人事労務管理上の悩みや問題点から、人材育成や評価、人員配置等の人事管理の方法や課題、起こってしまった労働トラブルの対応方法など、人に関わる事柄について多岐に渡り相談できるのが、「社労士の労働相談」です。
従業員の勤怠管理や給与計算、社会保険や安全衛生等、日々の労務管理業務に加えて、人材育成や評価、人員配置等の人事管理業務を行うにあたり、判断に迷う時、トラブルに繋がってしまった時、法的根拠を基にしたアドバイスができるのが、労働関係法令の専門家である社労士になります。
「どんな相談ができるのか、詳しく知りたい」「費用はどれくらいか知りたい」など、気になる方は、「ご相談フォーム」より、お気軽にお問合せください。
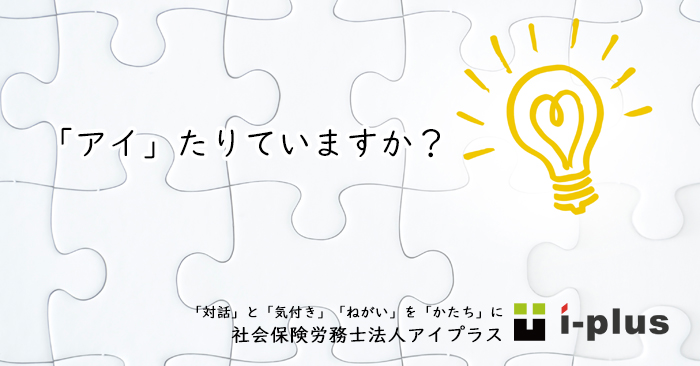
「人・組織のコンサルティング会社」
社会保険労務士法人アイプラス
2.労務研修の企画と実施
3.労務管理・労務トラブルの相談
3つの人事コンサルティングサービスを軸として、人事労務に関する課題の解決をサポートしている会社です。
ご相談フォーム
社会保険労務士法人アイプラス
東京都目黒区東山1-16-15 イーストヒル3F